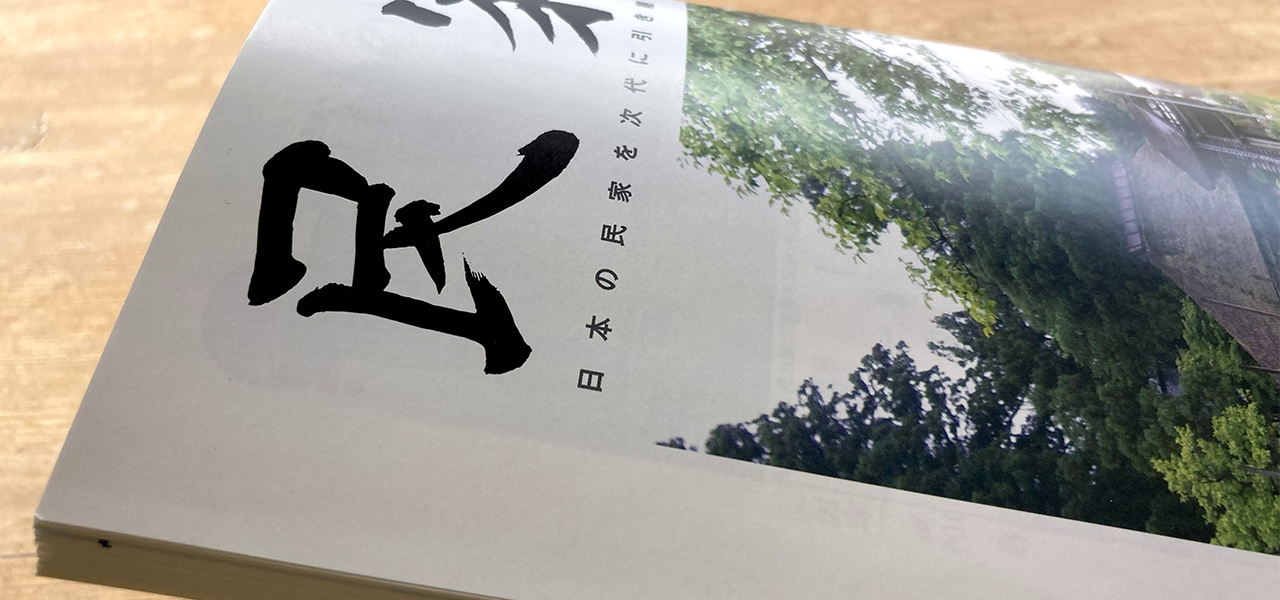
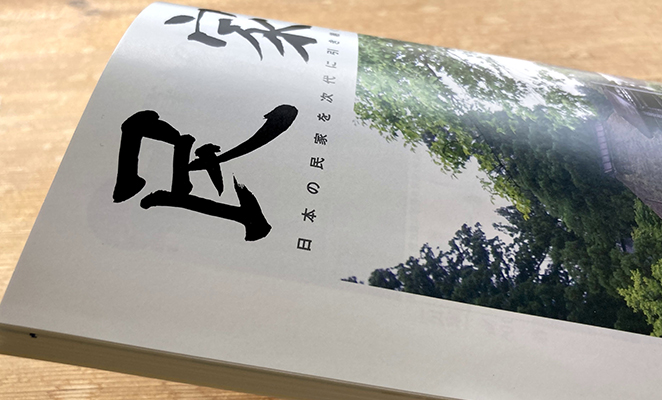
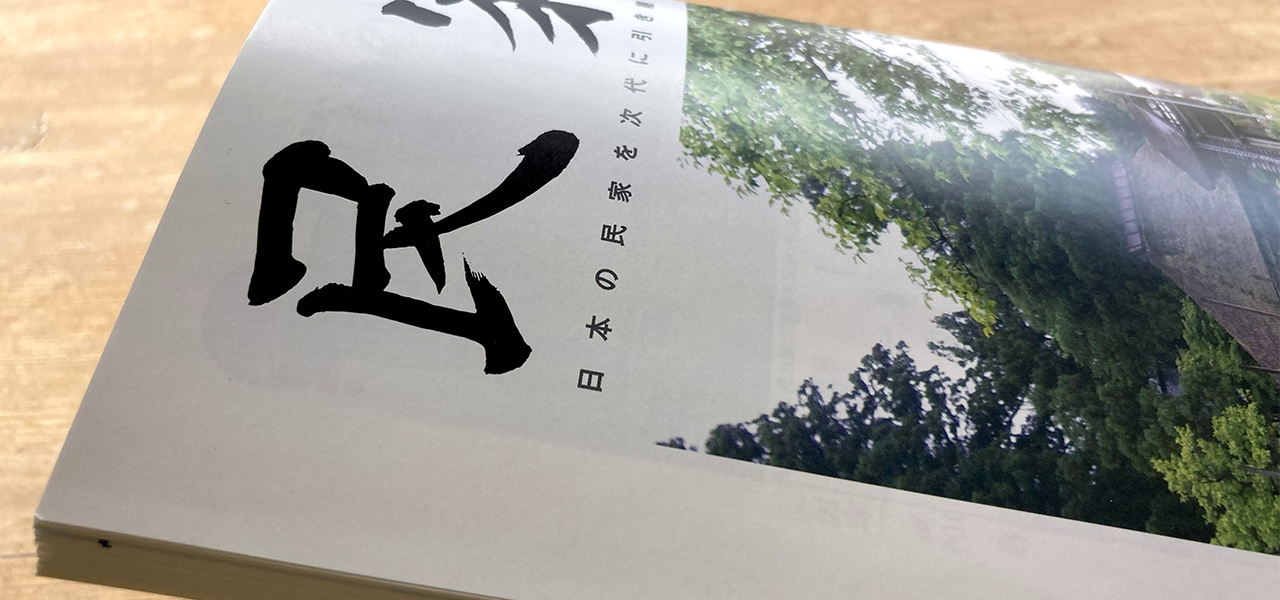
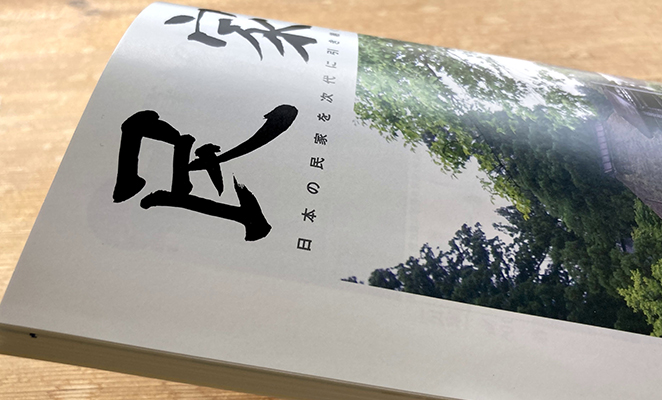

中国南部の民家
―日本の住まいの源流 2―
2020年11月29日(日)
参加:オンライン 69名 民家再生技術部会
第2回は揚子江流域の生活を漢民族に追われた、頓トン族と苗ミャオ族の習俗と建築を中心に勉強しました。数十年前に実際に現地入りし、生活を共にした講師ならではの視点と、現在までの研究成果で、いわゆる「原風景」をとらえての解説です。いま再度、取材しようとしても「近代化」の流れの中で、とても難しい状況でしょう。頓族の広葉杉との共生、高床式住居の木床上での直火使用の火災リスク、くつ脱ぎ文化などを記憶にとどめました。 (友の会会員H.H.)